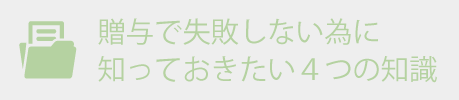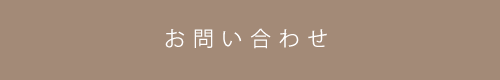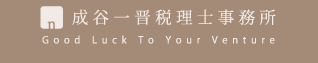-
基本的な業務
-
相続・贈与業務
-
こんな業務も
-
顧問契約について
-
お問い合わせ等
成谷一晋税理士事務所 > 相続・贈与業務 > 贈与に失敗しない為に知っておきたい4つの知識
贈与税の配偶者控除とは・・・

夫婦間で財産の移転がある場合には贈与税額を安くする特例があります。
この特例は、暦年課税の基礎控除額110万円とは別に、課税価格から最高2,000万円をマイナスすることができる制度で、次のような要件を満たす場合に適用が受けられます。
また、この居住用財産の贈与は、生前3年以内の贈与の場合でも、相続財産に加算しなくてよいことになっています。
① 婚姻関係が20年以上であること
② 居住用の土地や建物、居住用の土地や建物を購入するための金銭の贈与であること
③ 贈与を受けた年の翌年3/15までにその土地や建物に実際に居住し、その後も引き続き居住する予定であること
④ 過去にこの配偶者控除の適用を受けていないこと
⑤ 税額の有無に関係なく、贈与税の確定申告期限までに一定書類を添付して確定申告を行うこと
住宅取得等資金を受けた場合の非課税特例とは・・・
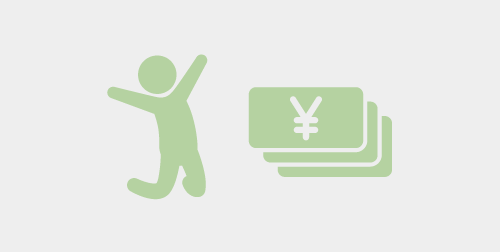
20歳以上の子(=受贈者)が父母や祖父母などの直系尊属(=贈与者)から一定要件を満たす住宅取得等資金をもらった場合には、その受贈者は一定金額(平成26年中は最大1,000万円)までが非課税となります。
① 適用を受けるための要件とは
・直系尊属である贈与者からの贈与であること
・受贈者は贈与を受けた年の1/1において20歳以上であり、その年の合計所得金額が2,000万円以下、そして贈与を受けた時に国内に住所を有していること
・受贈者が自己の居住用の土地・建物を取得するための資金の贈与であること、自己の居住している家屋の増改築等のための資金の贈与であること(※土地だけの取得は適用対象外、住宅用家屋の新築に際して先行取得する土地は適用対象となりうる。)
・贈与を受けた年の翌年3/15までにその資金をもとに取得した土地・建物に実際に居住すること、確実に居住することが見込まれること
・家屋の床面積50㎡以上240㎡以下の国内の新築または築後経過年数が20年以内の中古住宅等(一定の耐火建造物は築後25年以内)であること
・増改築後の床面積50㎡以上240㎡以下で増改築費用が100万円以上であること
・税額の有無に関係なく、贈与税の確定申告期限までに一定書類を添付して確定申告を行うこと
② 非課税限度額とは
住宅取得等資金の非課税限度額は、住宅の種類や贈与を受けた年に応じて、次のように設定されています。 (省エネ等住宅の場合)
・平成26年のとき・・・1,000万円 ※東日本大震災の被災者は1,500万円
・平成25年のとき・・・1,200万円
・平成24年のとき・・・1,500万円 (その他の住宅の場合)
・平成26年のとき・・・500万円 ※東日本大震災の被災者は1,000万円
・平成25年のとき・・・700万円
・平成24年のとき・・・1,000万円
③ 併用可能な制度とは
この非課税制度を適用した後の残額には、暦年課税の場合は基礎控除額110万円を、相続時精算課税の場合は特別控除額2,500万円を適用することができます。
相続時精算課税の場合は、贈与者の要件(年齢制限はないものの父母に限定されること)や家屋の床面積要件などが一部異なります。
非課税限度額とは
住宅取得等資金の非課税限度額は、住宅の種類や贈与を受けた年に応じて、次のように設定されています。
(省エネ等住宅の場合)
・平成26年のとき・・・1,000万円 ※東日本大震災の被災者は1,500万円
・平成25年のとき・・・1,200万円
・平成24年のとき・・・1,500万円 (その他の住宅の場合)
・平成26年のとき・・・500万円 ※東日本大震災の被災者は1,000万円
・平成25年のとき・・・700万円
・平成24年のとき・・・1,000万円
③ 併用可能な制度とは この非課税制度を適用した後の残額には、暦年課税の場合は基礎控除額110万円を、相続時精算課税の場合は特別控除額2,500万円を適用することができます。
相続時精算課税の場合は、贈与者の要件(年齢制限はないものの父母に限定されること)や家屋の床面積要件などが一部異なります。
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例とは・・・
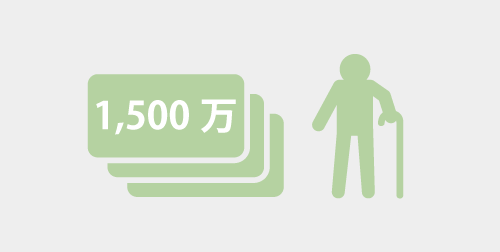
30歳未満の子や孫などが、祖父母などの直系尊属から教育資金として金融機関等との教育資金管理契約に基づいて、信託受益権を付与された場合や書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合等には、その子や孫ごとに1,500万円まで(学校等以外は500万円まで)が非課税となります。
子や孫などの受贈者が30歳に達した場合は、この教育資金管理契約は終了となり、「非課税とされた金額」から「教育資金として実際に支出した金額」を控除した残額がある場合は、その残額は贈与があったこととされます。
その金額は、受贈者の契約終了日の属する年の贈与税の課税価格に算入されるため、その年の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、所轄の税務署で贈与税の確定申告が必要となります。
なお、受贈者が死亡した場合は、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。
① 教育資金とは
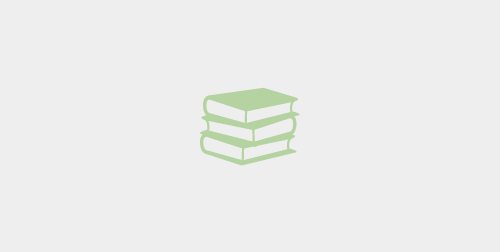
この制度の対象となる教育資金とは次のようなものをいいます。
・学校等に対して直接支払われる金銭等
・入学金、授業料、入園料、保育料、入学試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など
・学校等以外に対して直接支払われる金銭等で社会通念上相当と認められるもの
・学習塾、そろばんなどの教育費、施設使用料など
・スポーツ、ピアノ、その他教養を向上させるための費用など
② 適用を受けるための要件とは
・直系尊属である贈与者からの一括贈与であること
・受贈者は30歳未満であること
・金融機関等を経由して「教育資金非課税申告書」を納税地の所轄税務署長へ提出すること(※金融機関等での手続きで、税務署での手続きは不要)
・金融機関等から金銭等を払い出した場合、教育資金の支払いをした場合には、その教育資金に充てた領収書などを金融機関等へ提出すること(※金融機関等での手続きで、税務署での手続きは不要)
③ 教育資金管理契約の終了とは
受贈者に次のような事由があった場合、教育資金管理契約は終了となります。
・受贈者が30歳に達したこと
・受贈者が死亡したこと
・口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
相続贈与業務一覧
| 相続税対策 節税対策、納税シミュレーションetc |
|
| 相続税を理解するために必要な5つの用語 | |
| 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識 | |
| 相続税の申告に失敗しない為知っておきたい6つの知識 | |
| 税額計算にあたって知っておきたい8つの知識 | |
| 事業承継対策 弊社が考える自計化とは?自計化導入のメリットは? |
|
| 贈与税の申告 顧問契約して頂いている方も、そうでない方も |
|
| 相続時精算課税制度って何? | |
| 贈与に失敗しない為に知っておきたい4つの知識 |