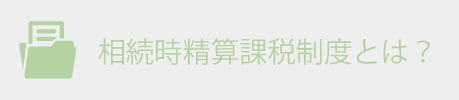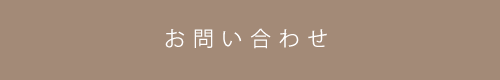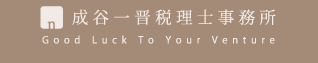-
基本的な業務
-
相続・贈与業務
-
こんな業務も
-
顧問契約について
-
お問い合わせ等
成谷一晋税理士事務所 > 相続・贈与業務 > 相続時精算課税とは?
相続時精算課税制度は、高齢者の財産を次世代にスムーズに渡せるよう生前贈与を促進するために設けられた制度です。
通常、贈与を受けた財産が基礎控除額110万円を超える場合には贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税はかからなくなります。
この制度の適用を受けるためには、贈与者や受贈者の年齢要件や必要書類等の一定要件を満たさなければなりません。
将来、この贈与者が亡くなった場合、その相続財産の計算ではこの制度の適用を受けた財産を加える必要があります。
この時の相続財産に加える金額は、相続が発生した時の価額ではなく、贈与した時の価額となっています。
計算の仕組み
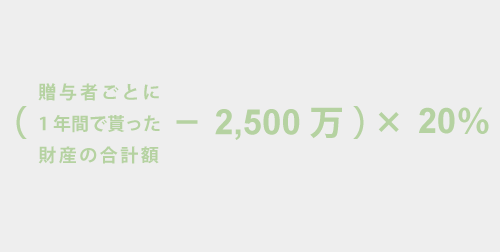
① 贈与税額の計算
・相続時精算課税を選択した場合、この方法を選択した贈与者(=財産をあげる人)ごとに、1/1から12/31までの1年間でそのもらった財産の合計額が特別控除額2,500万円を超える場合、その超える金額に対して一律20%が課税される計算方法をいいます。
・この2,500万円は複数年にわたって利用できる特別控除額の限度額となります。例えば、Aさんから前年に2,000万円、本年に1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合を考えてみます。前年の贈与における特別控除額は2,000万円、本年の贈与における特別控除額は1,000万円ではなく、500万円となります。
・相続時精算課税を選択する場合には、暦年課税とは異なり、期限内での贈与税の確定申告が必要となります。
・相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税(基礎控除110万円など)に戻ることはできません。
② 相続税額の計算
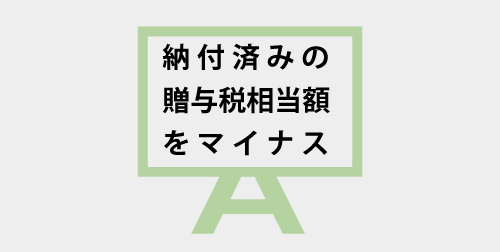
・相続時精算課税を選択し、その相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった場合には、相続・遺贈により取得した財産だけではなく、相続が発生するまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用財産を合計した金額をベースにいったん相続税額を計算します。
その後、この税額から相続時精算課税により既に納付済みの贈与税相当額をマイナスした金額が相続税額となります。
・相続財産に合算する相続時精算課税の適用財産は、「相続時の価額」ではなく、「贈与時の価額」を使用します。
③ 適用要件
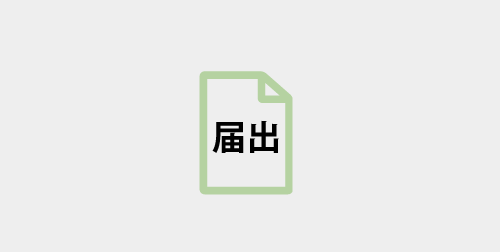
・相続時精算課税を選択することができる条件としては、年齢等の要件をクリアすること、「相続時精算課税選択届出書」や戸籍謄本などの一定書類を申告期限である2/1から3/15までに提出すること等が挙げられます。
・財産をあげる人(=贈与者)は65歳以上の親で、財産をもらう人(=受贈者)は贈与者の推定相続人である20歳以上の子であること等の要件もあります。
相続時精算課税のメリット
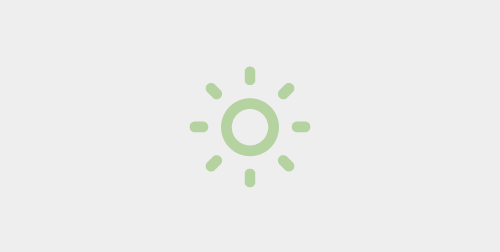
・2,500万円まで贈与税がかからない(暦年課税の場合は110万円まで)
・2,500万円を超える金額に対して一律20%(暦年課税の場合の税率は高い累進税率)
・財産の名義を受贈者に変更できる
・贈与時に比べて相続時の財産価値が値上がりすると見込まれる場合、相続時にはその相続財産の評価を下げることができる
・受贈者がもともと抱えていた債務を返済するためのまとまった資金を確保できる
・将来、相続税が発生しないと想定される場合、財産を早期に移転できる
・収益物件などを贈与した場合、その物件の家賃収入は贈与者から受贈者に変わるため、贈与者の相続対策だけではなく、受贈者にとって安定した資金が確保できる
・将来、経営者の所有する自社株が値上がりすると見込まれる場合に、その自社株を後継者に贈与することで、相続税対策と事業承継対策を行うことができる
相続時精算課税のデメリット

・この制度を一度選択すると、特定贈与者からの贈与を暦年課税へ変更することができない
・贈与時には贈与税がかからない場合でも、将来、相続税がかかる場合がある
・贈与時に比べて相続時の財産価値が値下がりする場合、相続時には値下がりする前の贈与時の価額で評価することとなる
・贈与財産が不動産の場合、不動産取得税などの移転コスト
・相続発生時に自宅などの小規模宅地等の特例が受けられない
相続贈与業務一覧
| 相続税対策 節税対策、納税シミュレーションetc |
|
| 相続税を理解するために必要な5つの用語 | |
| 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識 | |
| 相続税の申告に失敗しない為知っておきたい6つの知識 | |
| 税額計算にあたって知っておきたい8つの知識 | |
| 事業承継対策 弊社が考える自計化とは?自計化導入のメリットは? |
|
| 贈与税の申告 顧問契約して頂いている方も、そうでない方も |
|
| 相続時精算課税制度って何? | |
| 贈与に失敗しない為に知っておきたい4つの知識 |