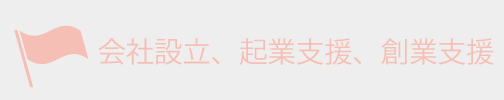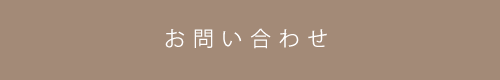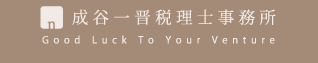-
基本的な業務
-
相続・贈与業務
-
こんな業務も
-
顧問契約について
-
お問い合わせ等
成谷一晋税理士事務所 > その他業務 > 会社設立・起業サポート
これから起業したい方、起業はしたけど事務作業に手が回らない方、将来の事業拡大を目指している方々が事業に専念できるようにサポートいたします。
事業計画・資金計画の作成、税務関係書類の作成など経営者の方がすべきことは多いため、我々税理士と連携を図りながら一歩ずつ進んでいきましょう。
1.「法人」か「個人事業」か?
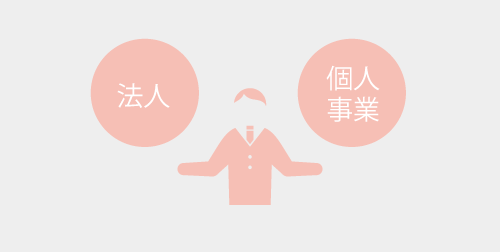
起業する際のポイントの1つに、「法人」で行うか、「個人事業」で行うかを十分に検討することが挙げられます。
「個人事業」でスタートした場合でも事業が順調に進めば、法人成りの検討も必要になります。
「法人」、「個人事業」のそれぞれにメリットとデメリットが存在します。
イメージだけで決めてしまうのではなく、今後の事業計画、資金計画、節税対策なども参考にしながら、総合的に選択することが望ましいです。
法人の場合は会社設立時に自社のルール、事業内容、資本金、事業年度などを決め、法務局等で登記手続きが必要になります。
この資本金や事業年度の決め方も簡単に決めてしまうのではなく、十分に検討した上で決定したいものです。
法人と個人事業主の違い
法人と個人事業主では税金の計算ルール、計算期間、手続き費用など、次のように異なる点がいくつかあります。
① 法人税と所得税
② 税金の計算対象期間(事業年度と暦年)
③ 資本金の有無
④ 法人設立費用(登録免許税など)
⑤ 設立手続き(法務局への登記など)
法人と個人事業のメリット・デメリット
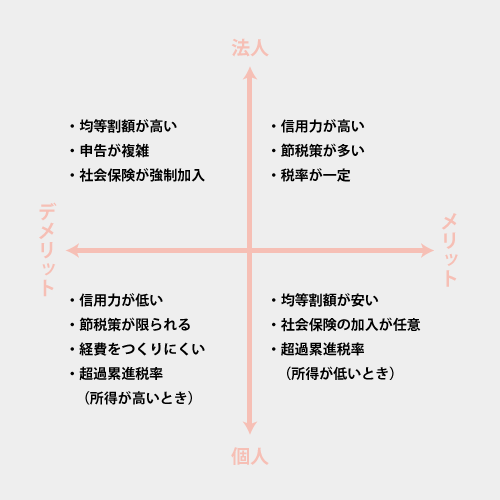
① 法人のメリット
・個人事業に比べて、対外的な信用力が高くみられる
・個人事業に比べて、第三者からの資金サポートを受けやすい
・個人事業に比べて、節税対策が多い
・所得水準が一定ラインを超える場合、個人事業に比べて税率が低くなる
・個人事業が1月から12月までの暦年で計算するのに対し、法人の場合は決算を自由に決めることができる
② 法人のデメリット
・赤字の場合でも課税される均等割額(都道府県と市区町村)が高い
・個人事業に比べて、確定申告が複雑で必要書類が多い
・社会保険が強制加入となり、資金繰りに影響を及ぼすことがある
・法人設立時に、登録免許税など初期費用がかかる。
③ 個人事業のメリット
・所得水準が低い場合、法人に比べて税率が低い
・赤字の場合でも課税される均等割額(都道府県と市区町村)が安い
・社会保険の加入は一定の場合には任意となる
④ 個人事業のデメリット
・法人に比べて、対外的な信用力が低くみられることがある
・法人に比べて、節税対策が限られる
・事業主の給与、福利厚生費など経費に算入できないものがある
2. 法人の資本金について
法人の場合は資本金をいくらにするか決める必要があります。資本金を1円とすることもできますが、対外的な信用力を考えた時に得策とは言い難いところがあります。
資本金の金額によって、会社にかかる税金が変わります。ここでは資本金が1,000万円、1億円を目安に税金がどのように変わるのかをいくつかご紹介します。
① 資本金が1,000万円以上の場合
・資本金1,000万円未満の法人に比べて、赤字の場合でもかかる法人住民税の均等割額(都道府県、市区町村)が割高となる
・設立1期目から消費税がかかる
② 資本金が1億円超の場合
・赤字の場合でも外形標準課税(法人事業税)がかかる
・中小法人に認められている優遇税率、優遇税制の適用が受けられなくなる
・特定同族会社の留保金課税の適用によって税負担が増える
3. 消費税の納税義務
消費税の納税義務は、その課税期間の基準期間における課税売上高で判定を行います。基準期間とは個人事業の場合は前々年をいい、法人の場合は前々事業年度をいいます。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、その課税期間における消費税の納税義務が免除され、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、その課税期間は消費税の納税義務者となります。
新たに事業を始めた場合は、基準期間が存在しないため、原則として消費税は免税事業者となります。
ただし、基準期間がない法人でも資本金が1,000万円以上の場合は、設立1期目からでも消費税の納税義務者となります。
基準期間がない法人で資本金が1,000万円未満の場合でも、平成25年1月1日以後に開始する年や事業年度については、特定期間の課税売上高・給与等支払額の金額次第で、納税義務者となることがあります。
4. 法人住民税の均等割額
都道府県、市区町村から課税される法人住民税の均等割額は、法人の資本金や従業員数に応じて、本店・支店の所在地ごとに課税されます。
① 大阪市内に本店がある場合⇒大阪府、大阪市から均等割額が課税される
② 大阪市中央区に本店、大阪市西区に支店がある場合⇒大阪府、大阪市中央区、大阪市西区から均等割額が課税される
③ 大阪市に本店、京都市に支店がある場合⇒大阪府、大阪市、京都府、京都市から均等割額が課税される
5. 事業年度・決算期の決め方
① 個人事業の場合、1月から12月までの1年間がその年の計算期間とされています。
② 法人の場合、定款で決算を自由に決めることができます。例えば、11月決算の場合は12月から11月の1年間がその年の事業年度とされています。
③ 法人の決算期の決め方
法人の場合は、原則としてその事業年度の所得をもとに計算した法人税等を、決算日から2か月以内に確定申告し、納税を行うことになっています。
法人税等の確定申告は所得税の確定申告に比べると複雑で、時間・手間・労力を要します。
そこで、決算時期から確定申告期限までの2か月間が法人にとってどのような環境にあるのかをイメージしながら決算日を決める方法、そして、消費税などの税制優遇面から決算を決める方法を提案しています。
誕生日や記念日などを決算日とされているケースもありますが、メリットがあまりないようであれば、税務署等へ決算日の変更手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
・お金の一番多い時期、少ない時期から逆算して決算日を決める
・仕事量の一番多い時期、少ない時期から逆算して決算日を決める
・消費税の免税期間を最大限に考慮して決算日を決める
弊社でお手伝いできること
1. 提携士業との連携(司法書士・行政書士・社会保険労務士)
2. 税務書類の届出
3. 創業融資(日本政策金融公庫) のサポート
4. 法人・個人シミュレーション
こんなお手伝いも
| 飲食店サポート 飲食店特有の税務取引にも精通しております。 |
|
| 輸出・輸入税務サポート 輸出、輸入で発生する税務は、税務調査で狙われやすい部分です。 |
|
| セカンドオピニオン 顧問税理士以外からアドバイスを多角的に受けたい場合! |
|
| 会社設立、起業支援 他の士業とも連携し、起業をサポートしています。 |
|
| 決算オンリー 顧問契約して頂いている方も、そうでない方も |