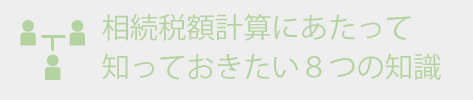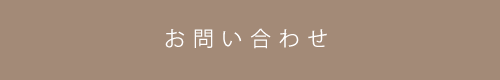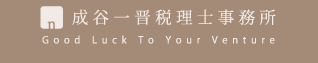-
基本的な業務
-
相続・贈与業務
-
こんな業務も
-
顧問契約について
-
お問い合わせ等
成谷一晋税理士事務所 > 相続・贈与業務 > 税額計算にあたって知っておきたい8つの知識
1.基礎控除額とは・・・
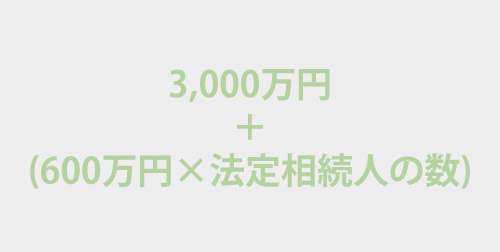
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)によって計算された金額をいいます。
被相続人の財産がこの金額以下の場合は相続税が課税されず、特例などの適用を受けない場合には相続税の申告は必要ありません。
2.法定相続人とは・・・

民法で定められた相続人のことをいいます。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者、子、父母や祖父母、兄弟姉妹になります。
相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になれますが、子(第1順位)、父母や祖父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は同時に相続人にはなることができず、相続人になれる順番が決まっています。
配偶者は婚姻期間に関係なく婚姻届を提出していること重要で、婚姻届を提出していない内縁関係の場合は法定相続人にはなることができません。
3.指定相続分とは・・・
被相続人の財産を相続人にどのように分けるかにおいて、予め遺言書で相続人の分け前を決めた分を指定相続分といい、すべての相続分に優先されます。
4.法定相続分とは・・・
被相続人の財産をどのように分けるかにおいて、遺言がない場合等に相続人同士が納得して分けるための目安として、民法で定めた相続人の分け前のことを法定相続分といいます。
民法で定められている法定相続分は次の通りです。
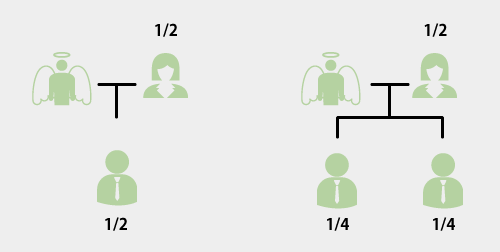
・配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/2
・配偶者と子2人が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/4、子1/4
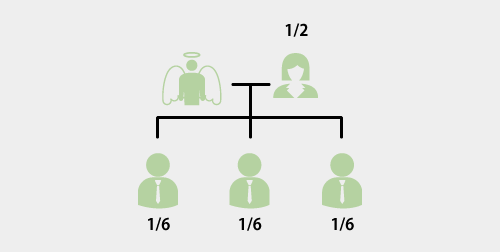
・配偶者と子3人が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/6、子1/6、子1/6
・配偶者と子3人(うち1人は認知された子)が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/6、子1/6、子1/6
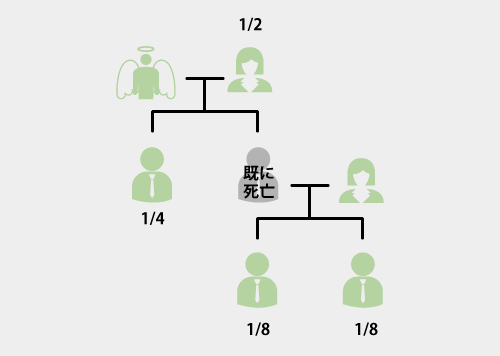
・配偶者と子2人、子のうち1人は亡くなっており、その孫2人が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/4、孫1/8、孫1/8
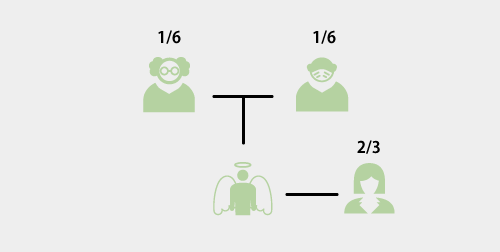
・配偶者と父母が相続人の場合・・・配偶者2/3、父1/6、母1/6
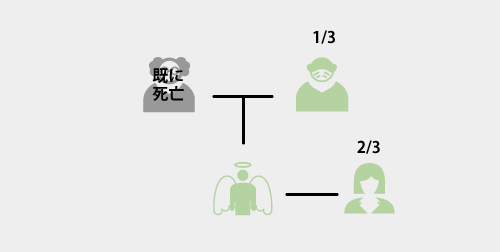
・配偶者と父母のどちらかが相続人の場合・・・配偶者2/3、父または母1/3
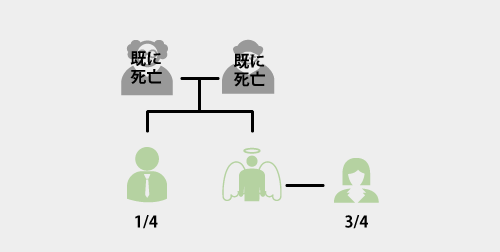
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
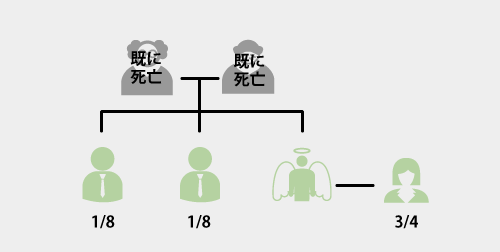
・配偶者と兄弟2人が相続人の場合・・・配偶者3/4、兄1/8、弟1/8
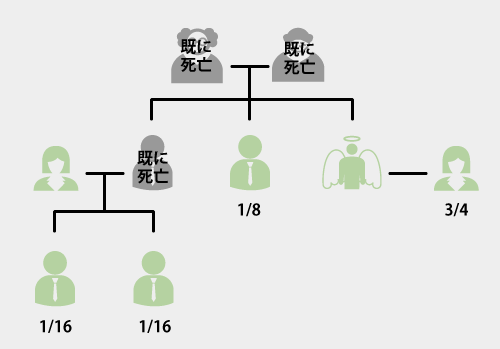
・配偶者と兄弟2人、兄弟のうち弟が亡くなっており、その甥が2人いる場合・・・配偶者3/4、兄1/8、甥1/16、甥1/16
5.遺留分とは・・・
遺留分とは、相続人が必ず相続することができる最低限の相続分のことをいいます。
例えば、被相続人が遺言書で特定の相続人1人だけにすべての財産を相続させると指定した場合に、その他の相続人が納得できないときには、その他の相続人は最低限の相続分を主張することができます。
この遺留分は配偶者、子、父母や祖父母だけに認められており、兄弟姉妹には認められていません。
民法で定められている遺留分は次の通りです。
| 相続人が配偶者だけの | 配偶者:被相続人の財産×1/2 |
| 相続人が子1人だけの | 子:被相続人の財産×1/2 |
| 相続人が子2人 | 子:被相続人の財産×1/4、子:被相続人の財産×1/4 |
| 相続人が子3人 | 子:被相続人の財産×1/6、子:被相続人の財産×1/6、子:被相続人の財産×1/6 |
| 相続人が配偶者と子 | 配偶者:被相続人の財産×1/4、子:被相続人の財産×1/4 |
| 相続人が配偶者と子2人 | 配偶者:被相続人の財産×1/4、子:被相続人の財産×1/8、子:被相続人の財産×1/8 |
| 相続人が配偶者と子3人 | 配偶者:被相続人の財産×1/4、子:被相続人の財産×1/12、子:被相続人の財産×1/12、子:被相続人の財産×1/12 |
| 相続人が父だけ 又は母だけ |
父または母:被相続人の財産×1/3 |
| 相続人が父母の両方 | 父:被相続人の財産×1/6、母:被相続人の財産×1/6 |
| 相続人が配偶者と 父または母 |
配偶者:被相続人の財産×1/3、父または母:被相続人の財産×1/6 |
| 相続人が配偶者と 父母の両方 |
配偶者:被相続人の財産×1/3、父:被相続人の財産×1/12、母:被相続人の財産×1/12 |
| 相続人が配偶者と 兄弟姉妹 |
配偶者:被相続人の財産×1/2、兄弟姉妹:なし |
6.相続税の計算の仕組みとは・・・
相続税は、次のように大きく3段階に分けて計算します。
・Step1・・・課税価格の計算
・Step2・・・相続税の総額の計算
・Step3・・・相続人ごとの相続税額の計算
Step1:課税価格の計算
まず、相続税がかかる金額がどれくらいあるかを次のように計算します。この相続財産の計算では「相続税評価額」を使用することが相続税のルールとなっています。
本来の相続財産+みなし相続財産+生前3年以内に贈与を受けた財産=相続財産
相続財産-非課税財産-債務控除=課税価格
※ 相続財産の評価は「財産評価に関する基本通達」に基づき計算を行います。この基本通達には様々な評価方法が定められており、土地等(借地権などを含む)、建物、株式、営業権などの評価は特に注意が必要です。
Step2:相続税の総額の計算
Step1で計算した課税価格の合計額、基礎控除額をもとに課税遺産総額を計算します。次に、法定相続人がこの課税遺産総額を法定相続分どおりにもらった場合を仮定して、仮定の相続税額を計算します。この仮定の税額の合計したものが相続税の総額となります。
課税価格の合計額-基礎控除額(※)=課税遺産総額
※基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円 (平成27年1月以降)
※基礎控除額=5,000万円+法定相続人×1,000万円 (平成26年12月まで)
課税遺産総額×法定相続分=法定相続人ごとの仮定の相続税額
法定相続人ごとの仮定の相続税額+法定相続人ごとの仮定の相続税額+・・・=相続税の総額
Step3:相続人ごとの相続税額の計算
Step2で計算した相続税の総額を、相続人が実際にもらった財産割合で按分したものが、相続人ごとの相続税額となります。相続人が実際にもらった財産割合は、課税価格の金額をもとに計算します。
相続税の総額×相続人がもらった財産割合(※)=相続人ごとの相続税額
※相続人がもらった財産割合=相続人の課税価格÷課税価格の合計額
7.税額控除とは・・・
相続税額が安くなるものとして税額控除があります。税額控除の主なものは次の通りです。
配偶者控除
「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」と1億6000万円のいずれか多い方の金額をマイナスできる。
贈与税額控除
被相続人から生前3年以内に贈与を受け、その当時に納付した贈与税がある場合、その贈与税額をマイナスできる、
未成年者控除
法定相続人が未成年者(20歳未満)の場合、その相続人が20歳になるまでの年数1年につき10万円をマイナスできる。
障害者控除
法定相続人が障害者の場合、その相続人が85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障害者の場合は1年につき20万円をマイナスできる。
相次相続控除
第1次相続(前の相続)と第2次相続(今回の相続)との間が10年以内の場合に、一定計算をした金額をマイナスできる。
外国税額控除
被相続人が外国に財産を持っていた場合に、外国において課税された相続税をマイナスできる。
8.遺産分割がまとまらないときは・・・
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、被相続人の財産を法定相続分で分割したと仮定して、相続税を計算し申告を行います。
その後、遺産分割がまとまった場合には、相続人全員が相続税申告の訂正を行います。
弊社がお手伝いできること
1. 相続発生前の対策
1. 相続人の選定
2. 相続財産の洗い出し、検証
3. 相続税額のご試算
4. 相続税額の節税対策ご提案
5. 遺言書の作成
6. 遺産分割案の検討
7. 二次相続対策
2. 相続発生後
1. 相続税の確定申告
2. 遺産分割
3. 二次相続対策、三次相続対策
5-1 相続税対策としてできること
5-2 相続税を理解するために必要な5つの用語
5-3 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識
5-4 申告に失敗しないため知っておきたい6つの知識
5-5 税額計算にあたって知っておきたい7つの知識
相続贈与業務一覧
| 相続税対策 節税対策、納税シミュレーションetc |
|
| 相続税を理解するために必要な5つの用語 | |
| 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識 | |
| 相続税の申告に失敗しない為知っておきたい6つの知識 | |
| 税額計算にあたって知っておきたい8つの知識 | |
| 事業承継対策 弊社が考える自計化とは?自計化導入のメリットは? |
|
| 贈与税の申告 顧問契約して頂いている方も、そうでない方も |
|
| 相続時精算課税制度って何? | |
| 贈与に失敗しない為に知っておきたい4つの知識 |